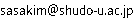|
前年度(2024年度分)の点検・評価項目
|
|
●1.授業の方針や授業計画と実際の授業の内容及び授業目標の達成度
|
|
すべての授業でシラバス通りに授業を進めることができた。しかし、2,3年の授業では、学⽣の基礎知識が乏しく,丁寧に繰り返しながらの説明を⾏ったため,少し授業⽇程とずれることはあった。また,応⽤編の授業として扱っている⾷料環境システム論でも学⽣の基礎知識が乏しいため,⾷と農に関わる問題の深い考察までできた学⽣が少なかった。応⽤系の授業の⽅法を⼯夫する必要がある。それ以外に、履修者数が多い授業 は、講演のような授業にならないような授業運営を意識していく必要がある。
|
●2.(1)教育内容・方法の工夫
|
|
学習時間の少なさを克服するため,課題を増やした。また,学習理解度を深めるため,授業冒頭での復習時間もより多く設けた。さらに,わかりにくい理論に関しては,図などの視覚的データを利⽤し,ミニクイズを⾏うなど理解を深める努⼒をした。書くことのみに注意がいかないよう、書かせてから説明をするように心がけた。そのほか、集中⼒を維持させるために、授業テーマについて受講⽣同⼠で議論する時間を設けるようにしたが、これが現在のところうまく機能しているように思われる。
|
●4.学生による本学の授業評価アンケートの実施、分析、結果の活用状況
|
|
授業アンケートをみると、講義⾃体への評価は良好であった。pptの図表・写真、リアクションペーパーを活⽤した基礎⽤語の説明などが好評であった。また、大講義であっても学生同士でテーマを話し合い発表させることを取り入れたことが、授業内容の理解を促進すると良い評価を得た。⼀⽅で、2324教室が暑いとの指摘があり、何度か教務課に伝えたが、なかなか状況が改善されずそれに関する苦情のコメントが多くみられた。教室が暑すぎて集中できない、といったものだが、他教室もあいておらず個人の努力では改善できないため、大学に改善を求めたい。
|
●5.公開授業の実施状況
|
|
地域環境論を公開し、参観者は0人だった。
|
●7.学生からの勉学(単位僅少学生への対応など)、生活、進路・就職などの相談への対応
|
|
3,4年のゼミ⽣は各2回,1回10分の⾯談を⾏い,各学⽣の進路や⽣活改善に対応した。それとは別に随時,学⽣からはメールや電話で相談があったので,全てに対応した。また,単位僅少の学⽣にも連絡をとり,勉学や⽣活の状況について⾯談した。公務員や留学を考える学⽣の相談にのり,準備⽅法などを指導した。
|
●9.学生の課外活動に対する支援(本学のサークルの部長・顧問としての活動)
|
|
該当しない。
|