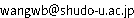|
前年度(2024年度分)の点検・評価項目
|
|
●1.授業の方針や授業計画と実際の授業の内容及び授業目標の達成度
|
|
授業方針と授業計画に基づき、各科目の授業を実施した。
講義科目の目標達成と工夫
講義科目では、受講者の授業内容に対する理解度を高めることを目標とした。授業では、毎回「授業資料」「授業参考資料」「パワーポイント資料」を配布し、必要に応じて編集した「映像教材資料」も活用した。
学生との対話を重視し、発言を促した結果、授業中の学生の発言が活発になった。これにより、受講者の興味を引きつけ、学習意欲を高めることができたと考える。その結果、受講者の授業内容への理解度向上に繋がった。
演習・ゼミナール科目の実践と成果
演習・ゼミナール科目では、レジュメ作成、発表、議論の方法を詳細に指導し、プレゼンテーションスキルの習得を促進した。学期当初はレジュメ作成やプレゼンテーション、議論に不慣れな学生が多かった。しかし、度重なる練習を通じて、学期末にはほとんどの履修者がレジュメ作成、プレゼンテーション、そして議論への参加が可能になった。
|
●2.(1)教育内容・方法の工夫
|
|
授業内容をより分かりやすく解説するため、以下の工夫を凝らした。
詳細な「授業資料」 を毎回作成し、配布した。
パワーポイント資料(図表、グラフ、写真、地図などを含む)を毎回作成し、それに基づいて解説を行った。
授業内容が難解な場合には、理解促進のために「参考資料」を作成・配布した。
必要に応じて動画教材を編集し、授業中に活用した。
上記の資料は、学生がいつでも利用できるようMoodleに掲載した。
授業の重要な部分は、特に丁寧な説明を心がけた。
授業規模の大小にかかわらず、すべての授業において受講者とのコミュニケーションが取れるよう、対話型授業を推進した。
授業前後および随時、メールやMoodleのメッセージを通じて受講者と連絡を取った。
演習・ゼミナールでは、プレゼンテーションの方法を習得させるため、テーマ設定から資料収集、レジュメ作成方法に至るまで細かく案内し、参考資料も紹介した。
プレゼンテーションや議論の方法を習得する目的で、細分化された項目を持つ「相互評価表」を作成し、学生間の相互評価と助言を行った。
|
●4.学生による本学の授業評価アンケートの実施、分析、結果の活用状況
|
|
学生による授業評価アンケートを前期と後期に分けて実施した。
アンケート結果を分析し、受講生の要望や改善点をまとめ、それを踏まえて授業の改善に努めた。
学部や大学が主催するFD(Faculty Development)活動などに参加し、そこで得た知見を自身の授業に結びつけて点検を行った。
|
●5.公開授業の実施状況
|
|
中国の歴史と社会を公開し、参観者は2人だった。
|
●7.学生からの勉学(単位僅少学生への対応など)、生活、進路・就職などの相談への対応
|
|
ゼミ生や留学生からの勉学・進路相談に丁寧に対応じた。
また、単位僅少者への面談を担当した。
|
●9.学生の課外活動に対する支援(本学のサークルの部長・顧問としての活動)
|
|
留学生会の顧問を担当した。
複数の留学生からの相談に対応した。
|